
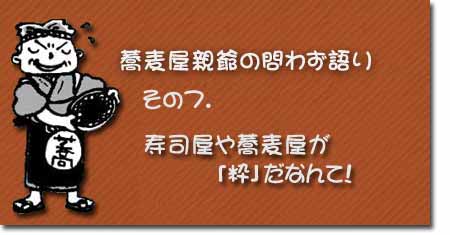
07.寿司屋や蕎麦屋が「粋」だなんて!

「粋」という字を店名にするのが、大変目立つ昨今だ。
インターネットなどで検索すると、恥ずかしいくらい「粋」という漢字を採った店名やウェブサイト名が多いのに辟易する。
かつて、「江戸前」という言葉がそうだった。
北海道なのに寿司屋で「江戸前」なんて看板をみかけ、首を捻ったものだった。
店主が若い頃東京で寿司屋修業をしてきたことを誇って、看板にしてるとばかり理解していた。
が、先代に鮨屋に連れてもらえる年齢になり、単なる宣伝文句だと知ったものだった。
そう思うと「粋」の字を使うのは「江戸前」という言葉ほどはミスマッチではないか、仕方がないかとも思うのだが、この乱用はなんともいただけない。
要は、「粋ごっこ」・「江戸前ごっこ」の世界でしかない。
では、その「粋」と「江戸前」って何なのか?が今回のテーマ。
今年は東京に行く機会が、なにかと多い。
毎月本州に業界会議や所用でいく。
東大にも観光学科が新設され、そこで国土交通省参事官が「観光学」の授業のコマを持ち、その最終講義で《観光コミュニティ》論で地域の観光まちづくりを抗議いや講義せよという、観光カリスマになるとこういう使われ方をされる。(^^)
行きのエアの機内圧に鼓膜を刺激され、気分が優れず羽田に着き、煙草も吸いたく戸外へ出たのが、・・間違いだった。
ベットリと肌に粘りつく蒸した空気に襲われ、更に具合悪くなりロビーの椅子で冷汗と脂汗を浮かべ吐き気に耐え気分が納まるのに思いのほか時間を喰い、たっぷり間に合って本郷に行けたのに、完全に抗議いや講義に遅刻しそう。
地下鉄本郷三丁目駅からキャスター付きバッグをひっぱり、歩道の人をかき分け駆け抜けながら、学生時代のデモ以来本郷界隈は必ず駆けなければならない運命だったのかと。
抗議いえ講義はそんなこなで時間オーバーの惨憺たる有り様で、学生さんには申し訳ない始末。
翌日は、色々蕎麦屋巡りをと計画していたが暑さにげんなり。
千歳行きエアの18:00の便を予約してあり、蕎麦屋を回って時間を潰したがそれでも余り、今は設計事務所を経営している学生時代の旧友を呼び出して一杯ということになった。再会した旧友は「寿司屋」に連れて行ってくれるという。
連れていかれた寿司屋は、店構えは現代風。
シンプルなグレーの壁面に、小さな入り口、渋い小さな浅黄の暖簾に、小さな屋号。
外観は合格の「寿司屋」だった、・・・が。
旧友に促され、暖簾をくぐった。
途端、浅草「ふじ屋」製手ぬぐいをねじり鉢巻した親方の、
「いらしゃぁいぃぃぃぃぃ」
と、バイオレンス映画の対戦車ミサイルのような迎え言葉が、襲ってきた。
防衛本能で自然に肩がいかり身構える程の・・・罵声だ。
威勢の良さと罵声とを、完全にはき違えている。
シマッタと思い店を出るかという顔をつくり旧友の顔を伺うと、全く気がついてくれてないで逆に、
「相変わらず威勢がいいねぇ」
と、客の方が愛想を言いへつらう。
「あたぼうよぉぉぉ、こちとら江戸っ子でぇぇぇ」
と、それほど広くない店内に響きわたるように、切り返えしてくる対戦車ミサイル「寿司屋」親方に、もう辟易し旧友をみる。
ところがわが旧友は、それが居心地がいいような顔を浮かべている。
二度目のシマッタという思いに、かられる。
「寿司屋」と客の間の「粋ごっこ」・「江戸前ごっこ」に逃げ出したい気持ちに、 襲われる。
江戸前や粋を履き違えた、技量もなく偏屈だけが売りの寿司屋親爺に、いいように莫迦にされてそれでいてマゾ的に喜んで、高価な代金を払って満足して帰る、完全にTVのグルメ番組の悪しき教育効果の精だ。
そもそも寿司屋の親方には、タイプがある。
先代がよく連れて行ってくれた鮨屋の親方は、概して物静かで鮨ネタに使えない個所を上手に料理した酒肴を毎日つくり、それとなく出してくれ、それがたまらないほど旨く酒がハカがいく料理だっし、そして握ってくれる鮨は、ふっくらとしたシャリの鮨だった。
が、昨今は何でもかんでも「江戸前」がまるで「粋だ」とはき違えているタイプが多くなってき、 この対戦車ミサイル親方は完全に後者で、こういう親方の握る「寿司」は 硬いシャリ加減が多く、まっぴらご免だ。
刺身が高価な瀬戸の器に盛られ、二人の前におかれる。
《おいおい、刺し身まで鮨ネタ切りでだすのか、江戸前は?》
と 咽から声が出かかるを 押さえる
さらに最悪な場面が。
これ見よがしに対戦車ミサイル親方が、明らかに死んだ赤貝をまな板の上に音を立てて打ち付け、音まで活きが悪い。
生きた赤貝を叩くならわかるが、もうクタクタになった赤貝だ。
旧友は よせばいいのに、
「お、赤貝かぁ」
と上手をいい 私もつい、
「検見川の赤貝?」
と言ってしまったら、
「あたぼうよぉぉ、江戸前でぇぇ」
と、またまた「江戸前」攻撃に曝される。
ふと悪戯心がムクムクとでて、
「あおやぎ、ある?」
というと、即座に対戦車ミサイル親方はまたまた、
「あたぼうよぉぉ、江戸前でぇぇ」
何を言っているのかという顔をする旧友ににやりと笑みを返し、その威勢のいい親方の前のカウンターに座るのは耐えられず、足を伸ばしたいと断り「こあがり」に移る。
「ったく!
検見川は千葉県だぞぉ、「あおやぎ」は別名「あられ」って言って青柳貝のこと。 名前の由来は千葉の青柳海岸で沢山採れたのでついたくらいだぜ。せいぜい羽田沖のアナゴなら江戸前と呼べるが、 千葉がいつ江戸前になった?」
と笑うと、旧友もつられて笑う。
言葉の端端に江戸前や粋という単語を挟み語りすぎる対戦車ミサイル親方に、流石の旧友も小声で、
「オマエも蕎麦屋だろうがぁ イキって何なんだぁ?」
と。
注文した日本酒の燗酒をあおった私は、顎でその日本酒の徳利を指し、
「これだよ」
「ン? 日本酒がイキかよ?」
「いいや、純米大吟醸の目ん玉飛び出る高い冷酒がメニュウにあっても、注文した燗酒はベタ甘の本醸造の安酒だ」
旧友は怪訝な顔をして、
「それがどうした?」
「この威勢のいい江戸前親方殿が、『つくってやる』と言いたげに出してきた刺身に、こんなベタ甘の本醸造の燗酒が合うか?
粋な『寿司屋』親方は、こんな酒をメニュウにはさんわな」
「・・・・なるほど、だな」
「昔はな、『寿司屋』の日本酒って、メインの鮨ネタこそを味わって欲しいから、それを邪魔するこんなベタ甘の日本酒など置かなかったわ。」
「ふ〜〜〜んンン」
「鮨がすすむ、食中酒の日本酒銘柄こそを厳選して置いたもんだが、こんなベタ甘なアル添の本醸造酒しかメニューにおかない寿司屋が、『粋や江戸前』なんぞ口にする資格はないわな」
「あははは、手厳しい」
「この刺し身の切り方も寿司ネタ切りだぞ、寿司はおって知るべしだな、オマエが大枚はたいてご馳走してくれるのはありがたいが、もういいだろ? 旨い日本酒を出す蕎麦屋に「お返し」で連れて行ってやる」
と、さっさと刺身を食べるよう、旧友を促す。
旧友は、それでも妙に親方殿にへつらい、
「親方ぁ、今日は親方の握りをと思って連れてきたんだが、コイツ今になって飛行機の便がもうすぐだって言いやがって、すまないがオアイソしてくれる?」
「ホ、お友達はどこから?」
「はぁ、北海道です」
「そりゃ残念だ、俺が握るなんぞ滅多にない、いつもは若いモンがこの時間握るんだが生憎休みやがって。
お客さん損したねぇ、折角俺が握るのにぃぃ」
旧友は頬をひくつかせ、
「・・・今度またの機会に連れてくるわ」
「そうだよ、折角俺が握るのに寿司も食べないで、お客さん運が悪いわ」
旧友のへつらう笑みが凍りついたのを、私は間違いなく見た(^^)
寿司も食べないで帰る客には、あの対戦車ミサイルの送り言葉はなかった。
背中をミサイルで撃たれないで、良かった(^^)
・・銀座1丁目のビルの地下に最近できた蕎麦屋に、向かう。
歩きながら旧友は、又
「粋な味って何なんだ? オマエ蕎麦屋だからわかるだろう?」
と呟いてきて。
最近こういう風にお鉢が回ってくる。
旧友にとっては、蕎麦屋や寿司屋そのものが「粋」という世界らしいが、
根本的に間違っている、そこに「粋」の難しさがある。
狭い階段を下り、屋号も何も書かれていない板戸のドアを開けてはいる。
女将が、黒のエプロンのユニフォームで迎えてくれ、カウンターに座る。
早速、純米酒「鷹勇」を「冷や」と「ぬる燗」で注文。
酒肴は、春の旬「桜エビのかき揚げ」を注文。
旧友は何か言おうとするが、私に目で制され酒がくるのを待つ。
女将は、カウンターに座る我々の目の前で、鉄瓶に徳利を入れお燗の温度計を徳利に入れる。 うぅ〜〜ん ここまでやるなら「ちろり」でお燗して欲しいが、まあ店それぞれだから・・・・ 。
旧友は、
「今の時代に 温度計で 燗の温度を」
「ええ、鷹勇を、それも《ぬる燗》で注文されるようなお客様は、燗具合が大事ですからね」
と、私に軽い流し目をしてき、旧友は女将と私を見比べる。
「オマエ、この店の 贔屓なのか?」
「いや、二度目」
女将が、
「確か 前回は 『ひこ孫』を?」
「いやぁ、覚えてくれてたとは」
うれしくなり、顔がだらしなくなるのを覚える。
酒が目の前に出て、旧友とやっと落ち着いて乾杯。
「冷や」といっても常温、それ「ぬる燗」と、互いに交互に差しつ差されつ、紫煙が漂うような時が流れる。
(この蕎麦屋、 禁煙なのが残念だ)
沈黙し、酒を味わっていた旧友は、
旧友の目は、遠くをみるようになる。
が、次第にシックなつくりの蕎麦屋の内装を商売柄チェックする目線になる。
無粋な商売目線をやめさせるのに、
「いつから、粋な店とか粋な料理なんていうようになったのかな?」
と、話題を振る。
「オマエの寮の部屋の本棚に、《いきの構成》とかいうそんな名前の本あったの憶えてるなぁ」
商売を忘れて、旧友はなんとか想い出モードにシフトチェンジ
「九鬼なんとかという人が書いた《いきの構造》だな、よく憶えてるなぁ、オマエは。
俺も学生時代読んだがな、そもそも当時のスッカラピンの学生が、《粋》なんぞわからんで読むのだから、何を書いているのか皆目わからんかったなぁ。」
「ハハハ、ヘルメットかぶってアジ演説するオマエが、あんな本読んでるかと。
みんな、マルクス・エンゲルス・レーニン、トロツキーだと、本棚に読みもせんのに並べて居た時代だ、正々堂々《いきの構造》ナンテ本があるオマエの本棚見てナ、 そのギャップに驚いてな、それで憶えてる。」
「まあ、今《イキ》って大いなる誤解の最たるものになってしまったな」
「粋な寿司、粋な蕎麦屋、粋な店、粋な女ってか、《粋》って漢字使った店名が溢れかえっている」
「ま、ウェブサイトやブログにも《粋》を履き違えて使っているの、 物凄い数で、粋のなんたるかを知っていたら、間違ってもその字を使わんだろうな」
「本当に《イキ》って何なんだろうなぁ?」
「そうだなぁ、《イキ》って【生き方】そのものだったハズだ」
「生き方か、そりゃちょっと難しい、自分の生き方さえ五里霧中なのに」
「江戸時代、幕府がおかれた江戸という町の、極めてローカルな美意識とでも言い換えるか」
「美意識ねぇ」
「生き方から、生活スタイルやファッションなんかに発展して」
「フゥゥム」
「で、そんな美意識に殉じた江戸の市井の人々が、鮨や蕎麦をたまたま好んだだけの話」
「たまたまかぁ?」
「だから江戸の料理などが、《粋》だったわけじゃない」
「オマエはそういうが、その九鬼ナントカ先生はなんていているんだ?」
「垢抜して(諦)、張のある(意気地)、色っぽさ(媚態)」
「ウムムム 難しい」
「簡単に言やぁ、《垢抜けした洒落た色気はもちろんだが、更に無理に無理を重ねて平気を装う》、そんなところだろう」
「宵越しの銭はもたない、ってやつか」
「だな、だから、もり蕎麦なんぞ江戸時代のファーストフードの典型だった。 それが今じゃ、一枚千円〜千五百円の蒸籠(せいろう)蕎麦なんて出回るわ、酒を一本に鮨を数巻ツマンデ数万円という時代になってしまったわ。
江戸時代の市井の町民が知ったら、抱腹絶倒の究極の《野暮》と笑ったわな」
笑いながら、桜エビのかき揚げに二人は舌鼓。
出てきた蒸籠蕎麦は、細打ちの蕎麦、蕎麦つゆはかなり薄め、
「こういう蕎麦をオマエは奨めるのか、違う気がするが・・」
と、旧友は小声で言う・
女将は板場に行っていたから聞こえないですんだが、マズイ!
「ヨソの蕎麦屋と比較するのは、店を出てからにするべ。 『粋』どころか野暮な客になる」
と私は話を必死に変わす。
「あのさっきの寿司屋、オマエの事務所の設計か?」
「あははは、ばれたか。 うちの若いスタッフが初めて担当した」
「あの表のグレー基調のデザインは、洒落ている」
「今な 結構グレーが流行ってな」
「不景気な時代、不安な時代は黒基調だからな。 グレーもその世界だ、黒からグレーになったてことは、少しは東京も景気がよくなって来た、ということだわな」
「ははは、オマエやっぱり建築に未練が」
「ははは、ない。ただな、色には興味あるわ、あのグレーは利休鼠だな。」
「利休鼠な、だな、そういえば、茶色や鼠色も《粋》の世界が作り出してきた、してきた色合いだ」
「それに一点、赤があればもっと粋にはなる」
「ははは、今回担当したスタッフはそこまで計算できない若者なんだ」
「寿司屋の暖簾を、赤基調の色合いにすればいい。」
「ホウ、それ貰うわ、今度担当者に言っておく。」
調理場から戻って来た 女将が参加してくる。
「最近は、本当にあか抜けたお店が多くなりましたね。」
旧友はやっと女将と話ができると、うれしそう。
「ううんん、その『あか抜ける』というのがね、難しい、今の若者に教えるのはもっと難しい」
「『あか抜ける』って言葉、何からきてるか知ってれば、教えるの簡単だ」
「なんだ。お前の、又知ったかぶりか?」
「ははは、酒の席の話だ、いいだろ。 上方は、きれいなものをどんどん身にまとい絢爛に、豪華にして着飾っていくんだ。 それにくらべると、江戸は省略していくことで勝負をする 文化なんだ」
「ウウムムム」
「だから上方の女性はきれいな色を好んで着るが、江戸の女性は渋めの柄ものを好み 『赤ぬける』と言って、赤い色など身につけなくても色気がでるようなファッション志向だった」
「じゃあ、なにか、『あか抜ける』は『赤ぬける』から来てるのか」
「と、謂われてるな。 もとは体を磨きこんで垢のない体にする、てぇ意味だったが、『赤なしで勝負する』、ってぇ意味も込めてる」


「へぇ、じゃあ、『江戸っ子は、赤は身につけないぞ』て粋がったわけだ」
「江戸の女の子にとっては、赤は最後の決め手、いや決め『色』だったんだ。 今日こそはあの人に、ってぇときに、初めて赤い紅(べに)をさしたり、赤い下着をつけていく、勝負のときのために赤はとっておく、逢瀬のときに赤い下着が、渋い黒っぽい無地の袖口や裾から、チラリと見せたら、男はドキリ」
女将が、
「赤い蹴出し(けだし:腰巻きの上に着る下着)がチラチラしてるって、江戸時代はなかったのですか?」
「普段、蹴出しの色は水色系だった、一般の女性は滅多に赤の蹴出しは 身につけなかった」
すっかり 酔いが回って来た旧友は、
「ホオオォォ、現代の日本の若い娘と同じだ。 赤の蹴出しは、江戸の娘たちの『勝負パ○ツ』だったんだ」
「まあ、そうも言えるかな。 兎に角、赤い蹴出しからチラリと見える白い足に、色気があり、足に白粉を塗るくらいだった、それで蹴出しの赤をよりアピールした」
「ウウムム、しばらくそんなシーンにお目にかかったこと・・ないな」
「あぁら、奥様にそうしてもらったら」
「恐ろしい事をいう、女将だ。 若い娘が、渋い着物に赤い蹴出しでなきゃなぁぁ、ウチの婆さんがやっちゃなぁぁ」
空いた器をさげる若いホールスタッフが、笑みを浮かべながら目だけは軽蔑のまなざしをくれる。
それから小一時間、旧友の建築の話に花が咲き、ころ合いを見て再会を約束し別れ、羽田にむかった。
私自身が「粋」でなければならないらしい蕎麦屋の親爺だし、好物は「鮨」だ。
冷酒で(おっとここでも誤解があるから正確に言うと)「冷酒=室温の酒」で一杯やりながら、鮨屋の親方が工夫した酒肴を楽しみ、もの静かな鮨屋の親方がふっくらと握る鮨を食べるのは、無上の喜びだ。
握り方がそうであれば、鮨は日本料理の華だ、とさえ思う。
しかし、である。
「室温の冷や酒」のつもりで注文しても、冷蔵庫で冷やしに冷やした「冷酒」を、それもスモモのような香り付けをした大吟醸酒を出されたら、もう興ざめになる。
たまには、女将孝行をと鮨屋に二人で行き、そんな冷酒を出されて、
「まあぁ、フルーティ」
などと、喜こんでくれるのはまあいい。
しかし、私の後頭部には、急速冷凍されたような白い塊が出来てしまい、その後のテンションを必死で高める努力に入らねばならない(^^)
羽田の、ANA側にしかないスモーキング・バーで、思いっきりエビスビールと煙草を楽しみ、帰りのエアにやっと搭乗。
もう暗闇になった窓の外を、酔いにまかせうつらうつら機窓から雲海を赤く染める夕日をぼんやりみながら、「粋」と「江戸前」の論議を反芻していた。
と、 前の座席から、どうやら小樽に向かうらしいカップルの会話が聞こえてきた。
「観光客で一杯の喧騒な観光施設なんか、いやだわぁぁ」
「じゃぁぁ、粋な寿司屋や蕎麦屋にでも、いくか」
「ま、こんないい女に有休とらせておいて、北海道旅行に行くのに蕎麦屋? 帰ったら会社の同僚に小樽で蕎麦屋に行ってきたナンテいうわけ、サイテー」
「バカ、今回は小樽でゆっくりお前と過ごすために、行くんだ。
地元客が通う寿司屋ならまだしも、観光客目当ての寿司屋なんかガッカリするに決まってる。 ましてやお土産品を買い回る旅などサイテー、オレとオマエでお土産話をつくりに行くんだろう」
って、いいねぇぇ、この男、旅をわかっている、こういうのが『通』だ。
千歳から小樽へそのカップルは、Uシートで仲睦まじい。
機内と電車でのビールが効き、レールの単調な音と振動が加味され、私は旅の疲れでうたた寝、JR小樽駅で駅員に起こされ、あわててホームに。
空気が旨い。 肌にべたついたりまとわりついたりしない、小樽がいい
店仕舞した直後の弊店に、やっと到着。
スタッフはあがり、女将がひとり帳場で帳面を。
「おかえりなさい」
「おお 帰ったわ」
「お疲れでしょう?」
「いや、エアと電車でたっぷり寝たから、店、忙しかったか?
2日も店を空けた蕎麦屋親爺としては、店も心配だ。
「スタッフのみんな頑張ったわよ、明日みな褒めてあげてください。」
「そうか」
「(売上のレジ精算伝票を見せながら)ね、私も頑張りました!」
「ん、えらい!」
髪のほつれ毛に手をあげて直す女将は、私のバッグと羽田で買った女将の好物・キースマンハッタンのチョコレート菓子とスタッフへのお土産の紙袋を受け取り、先にたって住まいの3階に階段をあがる。
目の前の階段をあがる女将の着物姿を見ながら、東京で旧友と一杯やった蕎麦屋の女将も黒のエプロンドレスではなく着物を着れば、もっと色っぽいのになどと不埒な考えを・・・
と、階段をあがるわが女将の、その着物の裾から普段は白か水色なのに『赤い蹴出し』が・・・・。
眠気がいっぺんに醒め、旅の疲れで機能不全・シナプス切断の脳がフル回転。
「や、やっぱり、なんだな、歳だな」
「ま、なんですか。そんな」
「つ、疲れてないと思ってたが、こうやって階段あがると、一挙に旅の疲れが・・・つ、つ、疲れたわ、クタクタだ」
「ま、さっきはそんな疲れてないとぉぉ」
いつになく、鼻にかかった声の女将。
居間に入り、ソファに俯せに倒れ込む。
あとは寝たふりだけしか、手はのこされていない。
疲れを偽装する背中に突き刺さる痛いほどの鋭い視線を後ろから受け、若い頃は逆だったのを思い出す。
《 揺り起こす 手を叩かれる あじけなさ 》
お粗末
(完)
