
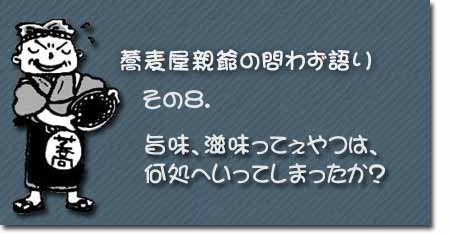
08.旨味、滋味ってぇやつは、何処へいってしまったか?
5月下旬、東京・国交省で、広域観光のポータルサイトづくりの報告をしてきた。
私の様なものの話を多くの方に聞いて頂き、感謝。
逆に、北海道の一地域で五年間展開されてきて、今新たな出発をする事業の宣伝・周知をする機会をもらい、その意味あいの方が私には大きい。
報告会のあと、港区三田で、小樽つながりの方々で懇親。
港区三田は、蕎麦屋親爺には、ただただ懐かしいエリア空間だ。
私の七年半の、眩しくめくらめく青春、学生時代のエリア空間だった。
田町や三田から足を伸ばすと、六本木、麻布十番があり、学生時代はよく歩いたものだった。
そんな懐かしい三田で懇親を深め、妙に里心が湧き上がる。
が、30年を経て、私の学生時代の痕跡はこのエリアには、もはや一片のかけらもない。
そして、蕎麦屋親爺に成り果ててからは、このエリア界隈での新感覚料理の飲食では、逆に苦い経験しかない。
案の定、翌日もそうだった。


旧友に連絡取る《前回は、変な寿司屋に連れて行って逆に恥かいたからな、今回はちょっと考えたんだぞ》と旧友力が入っていて。
前回の敵討ちだと、新感覚の日本料理店に連れて行ってくれて。
浅草や谷根千の庶民的店の方が、私はいいのだが・・・、
「オマエと俺だ、そんなにわか美食家振ることない、気楽な店でいい」
「だが、前回の寿司屋は大失敗だったから、信用回復しないとな」
と連れて行かれたのが、その日本料理店。
ビルの1F、内装は海外からのお客様を意識してか日本料理店を強調し、テンプラ建築ではなく細かいところまでしっかりとした造作、気配りの利いたセンス。
目も覚める白木のカウンターに座り、おまかせで料理が進んでいく。
日本酒、純米酒もおいてある。
燗酒を注文してもいやな顔をしないのが、いい。
椀料理がやがて、渋い漆塗りの業平椀の椀料理になって。
見た目、質素な椀の蓋をあける。
と、湯気の中に、椀の内側の金蒔絵が燦然と輝き目を射る。
まるで、粋な茶の小紋の着物姿の女性が、いきなりもろ肌脱いだら倶利伽藍もんもんの緋牡丹の入れ墨・・、「緋牡丹のお竜さん」状態。
蓋を開け、湯気があがり、真薯(しんじょ)の白さに焼き穴子が見え隠れしている。
旧友は既に椀を持って口をつけていて、熱いうち食さないと板さんに失礼という目で私を見返し、うながされて椀から立ち上る匂いを深々と嗅ぎ、口をつけた。
汁は、江戸前だから節のダシかと・・おもったら、京風スッポンの仕立てで。
今、長女が仲居修業に言っている関西の割烹料理屋では、新感覚の日本料理と銘打ちフォアグラやキャビアまで出す、とは聞いていたがこの店は白い真薯に黒いトリュフが。
目に滲みる取り合わせ。
気がつかない旧友に、【真薯にトリュフか】とそっと聞こえるように呟くと、
《うわぁ 真薯に トリュフかぁ》
感動している。
美食家なら鮮やかなコントラスト、とでも評するか。
しかし・・・
私には、若い女独特の辟易する匂い立ちのようにしか、感じられず、
【男を惑わせ目眩ませられる、若い女のフェロモンにも似た匂い立ちの料理だわ】
と小声で言うと 旧友は笑い、
《おまえ、学生時代の恋愛の苦い経験からまだ解き放たれていないのか、若いオンナのフェロモンもいいものだ 》
と、冷やかしてくる。
【口にしたとたん、スッポン仕立てのユリネと穴子の真薯という穏やかさの中にハレがある椀ものが、口中で鮮やかに瞬間的に広がる、まるで花火みたいな破裂感を与える椀ものになっている。日本料理が、今はこんなかと思うと、まるで北海道から出てきた田舎ものとしみじみ感じるな】
と いうと 旧友は 笑って。
数ヶ月前、同じ港区で名を馳せるレストランで、別の友人と久しぶりにと会食し、友人のお薦めで「DANCYU」でもよく紹介されている、有名なシェフのレストランに連れて行かれて。
その友人に言わせると《シンプルの極みをいく野菜料理が放つ圧倒的存在感的料理》だそうだ。
全共闘世代は、自身の位置づけを滔々と語る悪い癖がある、 ま、私もだが(^^)。
《季節野菜のオリーブオイル炒め・冷製》
なるメニュウを勧められて・・・

トレンドな新鮮さと鮮やかさと、まるで着飾った若いオンナのよう。
だが、カネにあかせて全国から有名野菜を引っ張ってこれば出来る料理・・と。
その友人には悪いが、最後まで水っぽさが残り、価格に比して豪華料理を食べた気がしないで終わって、別れた。
北海道の一地方都市の蕎麦屋親爺如きで、田舎者と笑われてもかまわないという気持ちで言いたい、
一体「旨味」や「滋味」って奴は どこにいってしまったのか
と 考え込む。
「旨味」や 「滋味」という感覚が、もう日本には向かない時代になっているのか。
そう小声で言うと、旧友が笑いながら、
《おまえ、それはもう五〇代を過ぎた男の郷愁だ、歳を重ねてきて失われていくもの対する郷愁なんだよ》
と 軽くいなしてくる。
【そうかな、この生き馬の目を抜く人のエネルギーを吸い取る東京という街では、旨味や滋味などと言ったら笑われるか?】
《ははは、オマエの挑発には乗らんが、そうだな、最近『旨味』や『滋味』なんて言葉とんと聞かないし、忘れているわな》
【有名料理屋に昔行くと、確かに取り合わせが斬新な食材で意表を突かれ目で食べるという言葉を実感させられる美しい精緻な料理だ、でも、じっくり咀嚼してみて、はじめてわかる、
『旨味、滋味』
という奴が、じんわりと唸りたくなるほど共存していたぞ、俺たちの若い時代は。】
《・・・ ウゥゥム、バブルで変ったかな》
【・・・ だな】
確かに、バブルの時代に料理は大きく変わった。
これでもかと高級食材をふんだんに使い、派手な演出で次々にテーブルに。
料理が華麗で何が悪いとでも言うかのように、口にすると舌を切る鮮やかな鮮度感と口中で炸裂する鮮烈さ。
しかし、時が過ぎ気がつくと、その鮮やかさと爽やかさと派手さは「軽さ」に映る。
猛烈に「旨さの濃かった」時代の料理が、懐かしい。
ただ濃いのではなく、旨さが濃い、滋味が濃く豊かな、バブル前の時代の料理が懐かしい。
味わいは実に濃いのに、決して重くはなかった料理に。
札幌の小料理屋で、お酒は「お一人3本まで」などと紙を張ってある料理屋に入り、席に着かず外に出たことを、以前本ブログで書いた。
「自信ある料理を用意しているのに、酒ばかり旨そうに何杯も飲まれたら、調理人がたまりません、ので」
「酒を飲み過ぎて、舌が麻痺して繊細な料理の味がわからないで食べてもらいたくない、と調理人が申しておりまして」
などと、ホールスタッフに言わせるなど、膝まつくことを客に要求するなんて。
この手の店では、酒に負けるレベルの弱々しい味しか出せない、ということだ。
酒を味方にし、食中酒とさせるような、旨さの濃い料理が欲しい。
今回の旧友が連れて行ってくれた銀座の新感覚日本料理の椀ものも、別の友人が連れて行ってくれた有名シェフのシンプルの極みをいく野菜料理が放つ圧倒的存在感的料理も、その鮮やかさと鮮烈さは、確かにある。
鮮やかさと鮮烈さと、その生っぽい軽さではない、調理をとことんやりきった上での旨さの濃さと軽さを併せ持った料理で、唸らせて欲しい。
・・・小樽には、かつてレストランが全盛の時代があった。
今、東横インの買収が噂されている「ニューみなとホテル」の前身は「小樽中央ホテル」といい、全道に和食職人を輩出したし、北海ホテル(現小樽グランドホテル)を頂点に洋食職人の確固たる世界が小樽にあった。
外国航路の貨客船のコック長をして、年齢から陸に上がって、レストランを開業するケースが結構あり、そんな街角の気取らない洋食屋に連れて行って もらうのが、子供心に唯一の楽しみだった。
普段は、酔って帰っては母と派手な夫婦喧嘩する父が、そういう時は背広に蝶ネクタイに変身するのを、子供心に誇り高く感じたものだった。

花園路地。
物心がつく年齢になると、小樽の街がポテンシャルを失い、和食職人は札幌にどんどん職を求めて離樽していき、北海ホテルは頑張っていたが、生意気な二〇代の私などが気軽に行ける洋食屋は、花園公園通りから路地を入った店くらいしか知らなかった。
その、路地裏の洋食屋のオヤジさんが作ってくれた
「ビーフシチュウ」
は、調理をとことんやりきった上での、濃さと軽さを併せ持った旨さと滋味の典型の料理だった。
未だに 夢見ることがある。
二〇代のまだ独身時代のとある定休日に、その路地裏の洋食屋に足を踏み入れる、と、
「おぉ、蕎麦屋の息子か。 今作りかけの旨いのあるから、食べていけ」
といい、分厚いアルミの片手鍋を懸命に振りながら、言ってくれた。
おそるおそる、何を創っているのかと聞くと、一睨みし「ビーフシチュー」と。
なんだ、ビーフシチューかと私はがっかりし、しかし飢えたガキのくせに生意気な私の表情を読み取ったオヤジさんは、
「お前んとこでもカツ丼はやっているだろう、旨いカツ丼をな、つくる、いい勉強をさせてやる」
と。
和のカツ丼と洋食の典型・ビーフシチューが、なぜ共通項をもつのか、チンプンカンプンで。
分厚いアルミの重そうな片手鍋を振るオヤジさんを見守り、待つこと三〇分。
立ち込める肉の匂いに、オヤジさんに間違いなく聞こえるくらいゴクリと喉が鳴り、いよいよ皿を棚から取り出し、真っ白い皿に。

・・・赤黒い肉の塊が・・・数個だけ。
【あのぉ・・、ビーフシチューでしたよね。
あの、ソースかけるの忘れて・・・】
「ソースは、・・・ない。
これを飲みながら 楽しむんだ」
といいながら 赤ワインを並々とグラスに注いでくれた。
話だけのオヤジなのかと、不埒にも若い私は思い、ナイフとフォークをとりその肉塊にナイフを入れようと よく肉塊に魅入ると・・・。
ビーフシチューのソースは一滴もないが、肉の周囲にキラキラ光るベールが纏わりつき透明なゼリーというか、よく見ると肉塊からにじみ出た脂分が、硝子の様な膜をつくり肉塊を覆っていた。
ナイフは勿論フォークを入れるのも 勿体ない。
オヤジさんは、黙って片手鍋から肉塊を他の皿に移していて、私など無関心のよう。
おそるおそるナイフを入れて、口に・・・。
歯を立てた肉片から、恐ろしいほど芳醇で濃厚なソースが溢れ、ジュワーっと口中に広がって。
肉汁と一体となったにじみ出るようなソースと、膜の様な脂分が一体となって、それに渋みのある赤ワインが加わる、三重奏。
肉には赤ワインという意味の真実を、その時私は生まれてはじめて理解した。
「欧州航路の客船のコック長から教わった 本場フランスのビーフシチュウ」
「それが 今 食べてるやつだ」
「ブッフ・ブルギニョン《Boeuf Bourguignon》 訳せば 《牛肉の赤ワイン煮込みブルゴーニュ風》ていうところかな、ま、ブルゴーニュ地方に限らず、フランスの代表的な家庭料理といっていいな。」
「それが、フランスでも次第に失われてきているのが、寂しい。 このソースをすっかり肉に閉じ込める料理方法は廃れて、本場でもソースひたひたのメニュウに成り下がっているらしい。 どの国も同じだな、堕落は。」
オヤジさんの話は、止まらなくなっていく。
「庶民のな、家庭料理だから作り方はシンプル。 ただ、諦めないで鍋を揺すり続けるのが、肝心な料理だ。」
「上質な牛肉といい赤ワイン、これがすべてだな、赤ワインをドボッと鍋に入れシチュウをつくっていく、味付けは最初はしないでな、で、頃合いを見て岩塩で味加減を見ながら中火で味の調整する。
ここからが、お前さんとこのカツ丼と同じ原理だな」
【カツ丼と同じ原理って】
「これだからな、お前さん毎日つくっている蕎麦屋のカツ丼の旨さはなあんだ? 肉の良さか、そんないい豚ロースなど使っていまい。」
【あ、ハイ】
《蕎麦屋のカツ丼が旨いのは、蕎麦つゆを味のベースにしてるからだが、お前さん『浸透圧』って学校で習ったろう?》
【し、 シントウアツ・・浸透圧、うぅん、ナンカ生物でならったな、細胞膜を濃い液体が行ったり来たり】
「頭はわるくないようだな、そうだ、良く憶えてたな。
が、普段自分が料理する世界でそれがあるのを知らない、耳学問なだけだな。 大学出はこれだからな。」
「蕎麦つゆ入れて、砂糖入れて、玉葱引いて、その上にトンカツを乗せて、落とし蓋で火にかける、だろ?
そのとき、トンカツとそばつゆが、丁々発止するわけだ。
最初は蕎麦つゆが濃いから、どんどんトンカツの中にしみ込んでいき、トンカツの中で肉汁と蕎麦つゆが馴染み合っていく、しかし煮込んでいくとトンカツの中の濃度が高くなっていくから、今度はトンカツから肉汁が出て、鍋の蕎麦つゆに馴染んでいく。
肉汁が出て蕎麦つゆと渾然一体なって、それを鍋の中で繰り返されて、蕎麦つゆと肉汁がトンカツの衣を通じながら旨味を増していき、その最高潮のところを溶き玉子を上からかけ、最高の旨味のところで全てを封じ込める」
【へぇー、カツ丼を創るって、そんなことやってるんだ】
「お前が、普段やってるんだ」
【へぇー】
「ははは、だから耳学問だけじゃ駄目なんだ、お前さんが言ったとおり細胞膜いや半透膜っていったかな、その膜を通して濃度の差で溶液が行ったり来たりする、ここまでは化学の世界、その行ったり来たり効果で、旨味を引き出すのが調理の世界だ」
この、ブッフ・ブルギニョンもおんなじだ。
中途で入れる塩加減で、肉から旨味の肉汁が出てきて赤ワインと混じり合っていいソースとなる、
このソースと一緒に肉を食べるのが、日本人がよく言うビーフシチュウだな。
が、このフランスの家庭料理のブッフ・ブルギニョンは、まだまだ食べないで中火で煮続けるところが、真骨頂だ。
赤ワインのソースで肉が煮込まれた頃合いを見て、鍋をただただ揺すり続けながらな、そうすると、今度はどんどん肉が赤ワインと肉汁が混ざったソースを吸い込んでいくわけだ、そう行ったり来たりするわけだ、この鍋を揺すり初める『頃合い』が、この料理の全てといっていい」
【カツ丼を溶き玉子で とじるタイミングですね】
「うん 少しはわかってきたな」

「いったん出て行った肉汁がソースを引き連れ肉の中に戻ってくる、それを助けるだけが調理人の役割。
ただただ肉を転がし続ける、そうしてるとソースは肉に吸われるのと、中火で熱せられて蒸発するのとで、やがてすっかりなくなる。
これを待って片手鍋を揺すり続けてきたんだ。
すっかりソースがなくなり、火でじりじりいう片手鍋をつかって、更に肉の表面を炒めるように転がしてやると、ついに、肉の内部から脂がにじみ出て来て、肉を覆うように透明な脂の膜をつくり、肉の中に吸い込まれたソースが滲み出せなくなるわけだ
このためにそれまで頑張って鍋を揺すり続けたわけだ。
フランス人は、この肉の中に閉じ込められたソースこそ、その調理人の人生そのものだ、と自慢するんだ」
オヤジさんの話と私の皿の肉が奇麗に無くなるのと、同時。
ビーフシチュウではなく肉を食べたという、満足感に浸りきる。
赤ワインで、軽く酔いが回り、重厚な濃い味のブッフの虜になって、しかし胃にもたれることもなくオヤジさんの店を後にした・・・。
ワインなどの酒にも一歩も引かず負けず、ただ濃いのではなく旨さが濃い、滋味が豊かに濃い。
味わいは実に濃いのに、決して重くはなかった。
今の時代では、体験できなくなった味だった。
・・・そんな若い時代の、小樽の洋食屋のオヤジさんの料理に思いを馳せて、語りすぎた。
私の話を、カウンター越しに板さんが聞いていたのに気がついて、慌てる。
〈ブッフ・ブルギニョン、いいお話をいただきごちそうになりました。 私もできることならそのオヤジさんの料理を味わってみたかった、です〉
と、板さんに言われ顔が赤らむ。
《ははは、そんな板さん、気にしないでいい。
こいつ、北海道小樽の田舎者の蕎麦屋のオヤジなんだから、戯れ言だよ.
お前がそんな話するから、板さんはおまえが洋食屋かと、緊張してしまってる.》
【そうだな、ごめんなさい、初老のオヤジの郷愁話だから】
〈あのぉ、北海道小樽で蕎麦屋さんを経営されておられるのですか?〉
【・・・やばい.】
〈あのぉ、ヤブハンってお蕎麦屋さんご存知ですか?〉
【・・・決定的にやばい.】
〈先日、観光で小樽にいったばかりで、そのヤブハンという蕎麦屋さんで、まあ、たっぷり蕎麦屋酒を楽しんできたばかりなんです.
小樽にあんな蕎麦屋があったとはと、失礼ながら感激しました.〉
《おい、お前の店有名になったもんだな。こんな板さんに知られているなんて!
板さん、この男がそのヤブハンの店主さ》
それから、板さんも交え昼間からしたたかに呑み、したたかに語って・・・。
旧友に礼をいい別れ、酔って歩く気力もなく、そのまま京急で羽田に。

エアの時間がまでたっぷりあり、ANAの2Fのスモーキングバーで、タバコをくゆらし、酔い覚ましのビールを飲んで、パソコンでメールチェックしながら時をつぶし、帰樽。
23:00、小樽到着。
帰店する。
まだ女将がレジで伝票の整理をしていて。
「おかえりなさい お疲れ様でした。」
「店は、どうだった」
「5月は最高です。スタッフのみんなもがんばってくれて」
「そうか、悪いな、五月は店を空けすぎたな。」
「アナタは、動く広告塔ですからね.今日も、後志の町の皆さん、小樽で会議があると わざわざ寄ってお蕎麦食べていただいて。」
「そうか、ありがたいな、そんな俺みたいのに、皆気を使ってくれて。」
「皆さん、商売投げて飛び回るアナタがいいみたいですね。」
・・・笑う、よりない。
「お食事の用意がまだなの、少し待っていただけますか」
「それじゃ、花園町のBでもいくか」
「あら、いいですねぇ、でもお疲れじゃ?」
「いいさ、じゃぁ早く行くべ」
居酒屋Bでは、最近廃業し解体工事が進む郷土料理「鱗」が話題に。
郷土料理「鱗」の建物は、旧キャバレー現代が「自養軒」というカフェの時代、そのカフェの女給さんたちの宿舎だった。
で、カフェ・自養軒がキャバレー現代に変わり、その自養軒の宿舎だった建物に駅前の「時代」という郷土料理店が移って「郷土料理・鱗」となり、現在まで営業してきたがGW前に売却された。
旧現代・旧郷土料理鱗・がつや島崎・丸証・籔半、と独特の路地裏空間を形成してきたが5階建てのアパートになる、と。
こういう、街角のランドマークが消えてしまう、切ない話はあとが続かなくなるので、料理の話になり、東京でしたブッフ・ブルギニョンの話を再度。
話は 盛り上がる。
「南の風」という名のカレーの店の話に花が咲く。
花園公園通りにあり、猛烈に辛いカレーだったが、先代が良く連れて行ってくれ小学生の子供心に辛さに中に旨さというものがある、のをその「南の風」のカレーで教えられた。
話に華が咲き、いい気分で帰途に。
酔いを冷ますのに、花銀を歩いて。
と、女将が腕を組んでくる。
深夜で、花園町は景気が悪いのか、人通りも少ないから、まあいいか。
「いい話でしたね 旨味と滋味のお話 」
「うん、蕎麦屋はどちらかというとあっさり料理という印象があるが、その旨味と滋味を 醸し出す料理の店であり続けたいな。」
「うふふ、ええ『アナタ』と一緒にそういう店づくりを、これまでも、これからもね」
《 ・・・きた! 》
女将モードではなく、女房モードにシフトチェンジしてしまってる。
いきなり、椎間板ヘルニアが疼きはじめ、腰がだるくなる。
「あのなぁ、東京一泊二日歩きづくめだったから、 あぁ腰がたがただな」
女将は、街灯も消えた薄暗い花銀の通りで組んだ私の腕を引き寄せる。
私の腕をつねりながら、

「そういうこと言うなら、私も黙っていられません」
「な、ナンダ」
「東京で召し上がった、超高級お野菜料理のこと」
「お前と一緒に食べなかったからって、怒られてもな、お前も知っている友人が連れて行ってくれたのだがら、仕方あるまい」
「そんなことじゃありません。 若い鮮やかだけど生っぽいオンナの味だ、などと言ってましたが、いつその若い鮮やかだけど生っぽいオンナの味を賞味したの?」
「ばか、モノの例えだ、それもオンナの味だなんてそんなこと言ったか、匂い立ちといっただけだ」
「同じことです」
「いい歳して、何言ってるんか」
「うふふふ、大女将が《夫を愛しなさい、でも、男としての夫を信じちゃいけない》って、お嫁に来たときに教えてくれたわ、外に出た男はなにするかわからない、って」
「ったく! 何十年前の話だ、それは!
姑が、息子の嫁にそんな洗脳するんか! 確かに俺の親爺は豪快に遊んだわ、女遊びもな、だからってお袋さんの亭主観を嫁に強制すんなって!
オヤジおふくろ夫婦と、俺たち夫婦は違う。」
「うふふ、そうですね、アナタ! 私達も、まだまだ旨味と滋味のある夫婦です。」
だめだ、話せば話すほど・・・ あり地獄だ
・・・体をすり寄せてくる女将の帰途の足が早くなる。
引きずられて帰る・・・私がいる。
(完)
